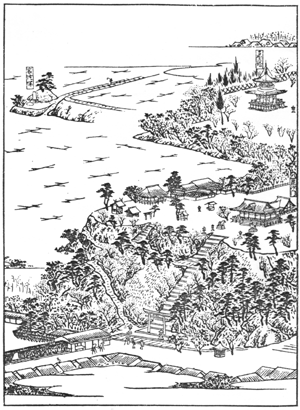
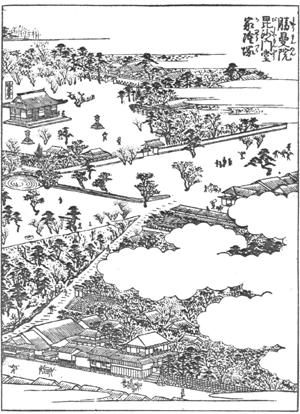
| 日本最初の社会福祉施設、施薬院(せやくいん)として建立 愛染堂の歴史は、今を遡ること1400年ほど昔の飛鳥時代、西暦593年(推古天皇元年)、聖徳太子は、敬田院、施薬院、療病院、悲田院からなる日本最古の官寺(国公式の寺院)として四天王寺を建立されました。 その中の施薬院は、あらゆる薬草を植え、病に応じてあまねく人々に与えられるようにと四天王寺の北西の角(現在の愛染堂の場所)に建立されたのです。当時の面積は現在より一層広大であり、また、建立の意味あいからいうと、我が国の社会福祉事業発祥の地とも言えます。 主な堂塔として、徳川秀忠(二代目)による再建の金堂(府の指定文化財)と、豊臣秀吉による再建の多宝塔(国の重要文化財・旧国宝)があります。 |
||||
施薬院から勝鬘院(しょうまんいん)へ 四天王寺の施薬院が勝鬘院というもう一つの名前を持っている経緯は、この場所で聖徳太子が勝鬘経というお経を人々に講ぜられた場所と伝わることから、勝鬘院(しょうまんいん)と呼ばれるようになりました。 勝鬘経は大乗経典の一つで、聖徳太子が熱心に翻訳と注釈書を残される程の日本仏教の基礎となる経典で、出家をしているかどうかに関わらず誰もが仏教を勉強する価値があるという内容が語られています。金堂内には、勝鬘経に登場する勝鬘夫人(シュリーマーラー)の仏像が祀られています。ちなみに勝鬘院の「鬘」は髭みたいな漢字ですが、「かつら」で漢字変換できます。 |
 勝鬘夫人坐像 |
|||
勝鬘院から愛染堂 また、当寺は「愛染堂」や「愛染さん」とも呼ばれ親しまれています。平安時代、弘法大師空海によって密教が日本に伝わると、金堂に愛染明王が本尊として奉安され、愛染明王信仰の普及とともに、勝鬘院全体が四天王寺の愛染堂と通称されるようになりました。 |
||||
愛染明王に手を合わせると、主に縁結び・良縁成就・夫婦和合・愛嬌開運の功徳があること、そして境内にある「愛染めの霊水」は飲むと愛嬌開運のご利益があり、願いが叶うといわれることから、良縁を求める参詣者が毎日たくさん訪れます。 また、小説家の川口松太郎さんが、この近くに住んでいたこともあり、彼の代表作であり映画化もされた『愛染かつら』のモデルとなった縁結びの霊木「愛染かつら」が境内にあることでも有名です。この霊木の前に立ち、愛を語り合った男女には、どんな困難な壁が立ちはだかろうとも、乗りこえ、何があっても幸せな結末が訪れるという素敵な伝説があります。 |
 |
 |
||

|